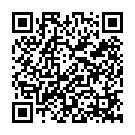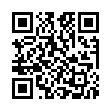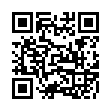「場合分け」にこだわる審査
クレームに「Aの場合、Bする」のような表現を記載することがあります。
この表現は、Aの場合はBするのであって、これ以上のことは何も規定していません。
つまり、Aでない場合にどうするかについては特に限定しません、ということです。
通常の会話では、例えば、「雨の場合は中止する」と言われれば、だれもが「晴れの場合は中止しない」と理解しますが、特許の表現は厳密ですね。
審査官も上記の意味でクレームを解釈することは言うまでもありません。しかし、中には、「でない場合」にこだわって審査されることがあります。(「場合分け」にこだわる審査などと言われます。)
「Aの場合については明確に規定されているものの、Aでない場合については、どのような動作をするのか不明確である」
のような拒絶理由を受けることがあります。
これに対して出願人は、真っ向から、「Aでない場合については、特に限定せずどんな動作でも構いません。どんな動作でも構わないという点で不明確ではありません。」と反論することもできます。
ただし、この対応は必ずしも審査官の意図に沿った対応とは言えません。無駄なやりとりで権利化が遅れるかも知れません。
審査官は、「Aでない場合について何も限定しないと、やたら広い発明になるのではないか」と考えているかも知れません。これはもちろん、その広い部分についてのサーチの手間を惜しんでいるということではありません。広い発明を特許して、無効理由を残してはいけないと考えるからです。
そうすると、上記の拒絶理由を受け取った出願人はどう対応するのがよいでしょうか。 (大人の対応?)
一般に、「Aでない場合」について、明細書に全く書いていないということはありません。
そこで一つの手としては、審査官に譲歩して、「Aでない場合」について、問題ないと思われるところまで記載することが考えられます。これは必ずしも発明を減縮するということではありません。むしろ発明を明確にするということです。明細書の書き方によっては、権利範囲を実質的に減縮することなく「Aでない場合」について書けることもあるかと思います。そのような対応を取れば、審査官も特許しやすくなるでしょう。
上記からもおわかりのように、出願時にクレームに「場合」を書くときには、「でない場合」について仮に審査官に指摘されてもいいように、明細書を工夫しておくとよいと思います。
ところで、こういう考え方もあります。
「場合」と書くと「でない場合」について聞かれるなら、「場合」を使わずに、例えば「とき」と記載してはどうかという考え方です。
「場合分け」とは言っても「とき分け」とは言わない?
一理あると言えなくもないですが、発明を記載・解釈する上で「場合」と「とき」に違いはないように思えます。それに、「場合分け」にこだわる審査に対して、単に「場合」を「とき」に補正したところで、拒絶理由が解消されるとも思えません。
実務的には、「場合」と「とき」の区別を考えるよりも、技術思想として、「でない場合」、「でないとき」をどう考えてクレームするかの方が大事だと思います。
(もっとも法律用語としては、「場合」と「とき」は若干違いがあるようで、「場合」は条件の中身が大きいときに使われ、「とき」は条件が小さいときに使われるようです。)
(元特許庁審査官 弁理士 田村誠治)
 東雲特許事務所
東雲特許事務所