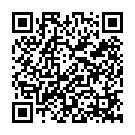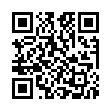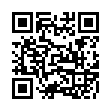審査官のロジックを再現してみる(2)
「記」の部分があまりに省略されすぎていて、29条2項の「記」としては疑問に思えるものもあります。一例を挙げましょう。本願発明は「機能Aを備えた受信機」とします。
これに対して、「引用文献○には、機能Aを備えた送信機が記載されており、よって、機能Aを備えた受信機は、容易である。」と「記」で指摘されました。
こうした拒絶理由を目にすることもあるかと思います。果たして、本願発明は、引用文献○を主引例として容易なのでしょうか。
上記例の記述中の「容易」は、日常用語の「容易」(審査官の主観)であって、特許法や審査基準における「容易」(客観性を有するもの)ではないようにも思えます。
もし、審査官の主観の「容易」に対して反論しなければならないとしたら、極めて困難です。そんなことを出願人に求めるはずはありません。
上記例から、審査官のロジックを再現するとこうなります。
「引用文献1には、一般的な受信機の発明(引用発明1)が記載されている。」
「引用文献1には、送信機に備わっている機能と同様の機能を受信機に備えてもよいことの示唆がされている。」 ★審査基準の一例です。
「引用文献2には、機能Aを備えた送信機が記載されている。」 ★上記の引用文献○です。
「よって、引用発明1の受信機に機能Aを備えることは容易である。」
このロジック中の最後の「容易」は審査基準における「容易」です。
よって出願人は、このロジックの不備を探して反論すればよいことになります。
以下は、蛇足ですが、
・結局、本願発明は、引用文献○に記載の発明(送信機の発明)から容易だったわけでなく、引用文献1に記載の発明(一般的な受信機)から容易だったということになります。(審査官はこのような考え方を「ベースが同じものを主引例にする」とか「ベースが異なるとロジックを組みにくい」などと言うことがあります。)
本願発明が「一般的な受信機から容易」ということに違和感を覚えるかも知れません。しかし、この違和感は、審査基準の「容易」が日常用語の「容易」とは意味合いが異なることに起因しています。そう考えて慣れてください。
・審査官は、わざわざ一般的な受信機の文献を主引例にしなくても、出願人なら理解できるだろう考えて、上記例のような「記」を書きますが、厳密には拒絶理由の「記」として必ずしも適切とは言えません。ただし、出願人としてもこの点を争ってもあまり意味がないので、その辺は理解した上で、審査官のロジックを再現して反論すればよいと思います。
(元特許庁審査官 弁理士 田村誠治)
 東雲特許事務所
東雲特許事務所