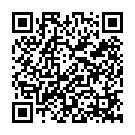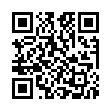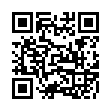シフト補正で損しないために
シフト補正きびしいですね。ちょっとした事例をご紹介します。
【請求項1】A+Bであることを特徴とする,装置。
【請求項2】前記Aはaであることを特徴とする,請求項1に記載の装置。
【請求項3】前記Bはbであることを特徴とする,請求項1又は2に記載の装置。
この場合,審査において,技術的特徴(STF)の有無が判断される順番は,
A+Bの発明(請求項1に係る発明)
a+Bの発明(請求項2に係る発明)
a+bの発明(請求項2を引用する請求項3に係る発明)
です。
審査の結果,請求項1,2に係る発明にはSTFが無く,請求項3に係る発明にSTFが発見されたとします。
この場合,拒絶理由通知には,「請求項3に係る発明のうち,請求項1,2に記載の発明特定事項をすべて含む発明とすることを検討されたい」のように記載されることになります。
そうすると,拒絶理由通知を受け取った出願人としては, a+bにさらに何かを加えて限定しなければならない,と思うのが自然です。
ところで,請求項3には,請求項2だけでなく請求項1を引用する発明も含まれています。
A+bの発明です。この発明を生かして補正することはできないでしょうか。
例えば,補正で,
【請求項1】A+b+xであることを特徴とする,装置。
【請求項2】前記Aはaであることを特徴とする,請求項1に記載の装置。
とする補正は,シフト補正でしょうか。
補正後の請求項2は,a+b+xですから,上記の補正の示唆に従っていますね。
では補正後の請求項1は?
厳密に言えば,補正後の請求項1は,補正前の請求項1,2とは単一性がありませんから,シフト補正になります。しかし,仮にxに特許性がある場合に,果たして審査官は,シフト補正のみを理由に拒絶するでしょうか。
シフト補正の示唆は,その示唆に従えば少なくともシフト補正になりませんよ,という最低ラインに過ぎません。従えば安全だけど,従わなくても何とかならかいかな?と考えてみるのも良い勉強になりますね。
とはいえ,上記の事例では実際は怖くてできないと思います。あとは必要な権利範囲との兼ね合いですね。仮にシフト補正が通知(最後の拒絶理由で)されたら,そのときに削除すればよい,と考えることも可能だと思います。請求項の記載順序を工夫するのも手かも知れません。
(元特許庁審査官 弁理士 田村誠治)
 東雲特許事務所
東雲特許事務所