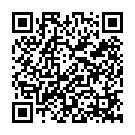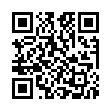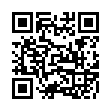補正の示唆で無効理由?
拒絶理由通知で「補正の示唆」がなされることがあります。
補正の示唆に従えば、通常はそれで特許になります。審査官も忙しい中わざわざ示唆してくれたわけですし、出願人としては救いの手を差しのべてくれたと考えるのが普通でしょう。補正の示唆がされたら、あまり考えずにそのまま従うという出願人も多いことと思います。補正の示唆に従わなかったら、審査官の心証を害して拒絶されるのではないかと心配になることもあると思います。
ところが、補正の示唆が必ずしもありがたいと思えない場合があります。
一番多いのは、補正の示唆が、クレームを限定しすぎている場合です。
この点についてはまた別項で述べます。
もう一つの場合は、希なケースとも言えますが、補正の示唆の内容が、
こんな補正して大丈夫なの?(違法じゃないの?)という場合です。
①補正の示唆の内容に従うと違法だけど、無効理由にはならない場合
②補正の示唆の内容に従うと、無効理由を有する場合
に分けて考えます。
①補正の示唆の内容に従うと違法だけど、無効理由にはならない場合
このような場合の典型的なものとして、最後の拒絶理由通知の際の補正なのに限定的減縮になっていない場合と、シフト補正になる場合があります。
この場合は、補正の示唆に従って大丈夫です。無効理由ではないのですから、本来なら違法だけど特許しますよという審査官のメッセージに従いましょう。
限定的減縮になっておらず補正を却下したり、シフト補正で拒絶したりできるのは、その補正をした審査官だけであることを考えれば、補正の示唆に従った出願人に不利な対応を審査官がするはずはありません。もちろん、無効理由ではないので、特許後に第三者がそのことを咎めることはできません。
このように書くと、まるで裏技みたいに聞こえるかも知れませんが、実務的にはよくあるケースです。
②補正の示唆の内容に従うと、無効理由になる場合
こちらは希なケースと思います。
審査官ができるだけ広い範囲で特許したいと考えて補正の示唆をしたものの、客観的にはサポート要件違反だったり、新規事項追加になっていたりすることが起こりえます。また、審査官の示唆がやや抽象的な場合など、補正の示唆に従ったはずの特許が、結果として無効理由を有するケースもあります。
これはもちろん問題です。審査官がどれほど大丈夫と言ったところで、無効理由のある特許は無効され得ます。
そこでこの場合は、補正の示唆をした審査官と十分にやりとりをして、無効理由を有しないようにすることが大事です。補正の示唆をした審査官はその時点で、この出願については最終的に特許するという心証を抱いています。このような出願に対しては、審査官もいつも以上に好意的に対応してくれるはずです。
(元特許庁審査官 弁理士 田村誠治)
 東雲特許事務所
東雲特許事務所